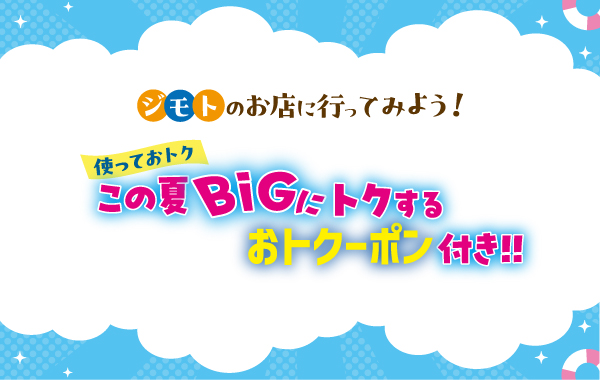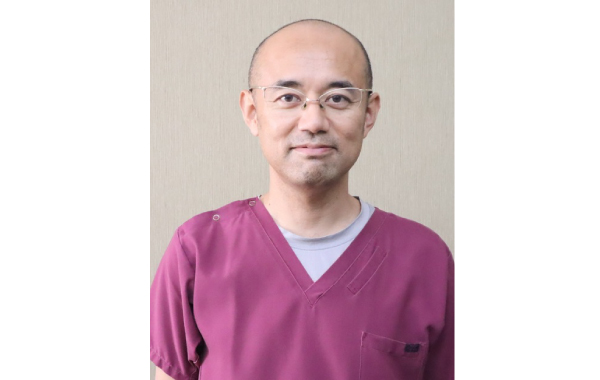江戸川区にある青森大学東京キャンパス(清新町2)で3月16日(日)、高規格避難所開所訓練が実施された。これは「災害関連死を抑え、女性にやさしい避難所(高規格避難所)」の実現を目指す同大学が、地域の学校や自治会、江戸川区、民間企業、日本赤十字などと共に開催したもので、約70人が参加した。
◆水害リスクの高い江戸川区
江戸川区民の中で地震への対応や備えについての周知はかなり進んでいるが、水害リスクについてはどうだろうか。荒川が氾濫した場合は区内の9割が水没し、水が引かない水没期間は2週間に及ぶと推測されている。
区内では高所にある同キャンパスは、避難所に指定されており、収容人数は2000人。しかし、災害時にはそこに2万5000人もの避難者が集まると予想されている。
リスク管理を専門とする同大学の久保英也教授は、相当な混乱が予想されるとし、「そんな中で、住民自らが避難所を開設し運営する手順、そして避難して来た人を災害関連死させない方法や設備を、この訓練を通じて知ってほしい」と話した。
◆シミュレーションゲームを活用
避難者の各々のプライバシーが配慮され、高齢者や小さな子ども連れ、移動が困難な人、体調不良者、女性なども体調を悪化させずに過ごせる場所、それが高規格避難所だ。
参加者はまず、「避難所運営シミュレーションゲームHUG」を使って、避難所の運営を疑似体験した。避難所のレイアウトから始まり受付での注意事項、避難して来た人をどんな意図で配置するか、共通ルールの示し方など、ゲームを通じて日本赤十字職員がていねいに解説した。
◆高規格避難所の見学
その後、体育館に設置された高規格避難所の設備を見学。避難者をスムーズに受け入れるために開発された避難者受付システムの内容を聞き、実際にスマートフォンや免許証を使って試した。
室内テントや段ボールベッドをはじめ、通信を確保するためのアンテナや携帯充電設備、子どもの遊び場の確保、アプリを使った災害情報収集方法、水循環型シャワーや移動式手洗いスタンドなど、災害時に役立つさまざまな展示を見た。参加者は皆真剣な面持ちで「手洗いスタンドの、水の入れ替え頻度はどのくらい必要ですか」などの質問も相次いだ。
さらに避難所で問題になるトイレ関連にも触れ、詰まりの心配なく使えるマンホールトイレを紹介。キャンパスの敷地内に設置可能であることや、設置の手順についても伝えられた。
終了後、「いざという時、自分は避難する側だと思っていたが、受け入れる側にもなると気づいた」「住民だけでなく旅行者も避難して来ると初めて認識した」など、参加者からはさまざまな感想が聞かれた。