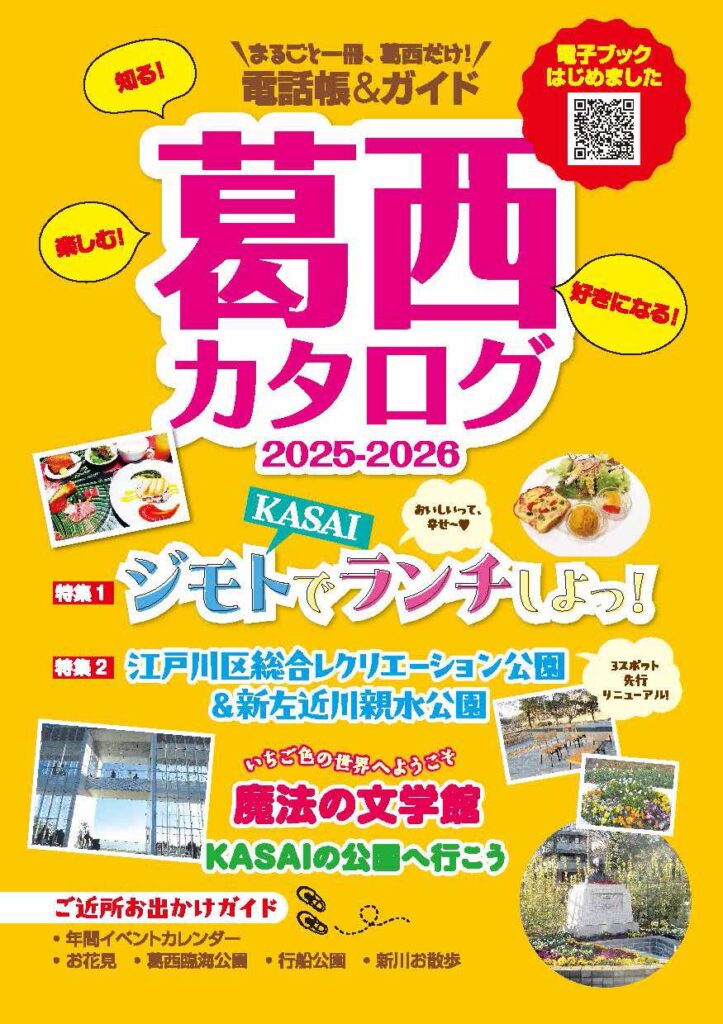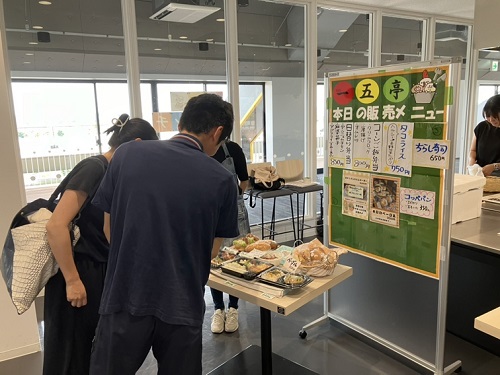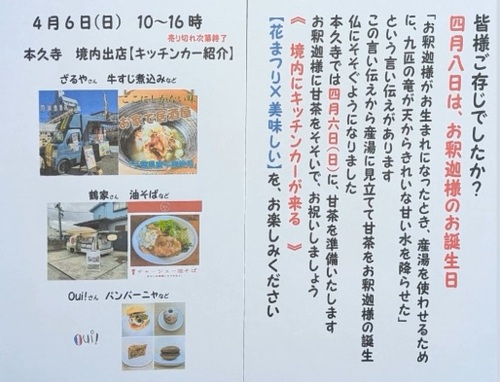国分・曽谷から八幡まで約10㎞を歩いた
3月8日(土)、市川街歩きの会(原田良博代表)主催の「第15回市川街歩き」が行われた。
同会は2017年にスタート。当時を振り返り原田さんは「市川市は大きく分けると、行徳地区、本八幡地区、国府台地区、大野地区になる。同じ市内に住んでいても、ほかの地区を知らないことが多い。街歩きを楽しみながら、それぞれの地区の文化や歴史、地理を再発見したいと思い、会を立ち上げた」と話す。
会員は現在約1400人。そのうちの50人がこの日、集合場所の「道の駅いちかわ」に集まり、雨が心配される中、配られた資料を手に街歩きに出発した。
◇
初めに訪れたのは、秀光人形工房市川店(国分6)。店内には時節柄、端午の節句の五月人形がずらりと並んでいた。すべて、全工程を手作業で仕上げたものだという。
続いて国分川調節池を経て弁天池公園(曽谷2)へ。弁天池は国分高校から東に向かう谷津の頭にあたる所にあり、曽谷貝塚の縄文人が飲料水として利用したといわれている。そしてその縄文人たちの遺した曽谷貝塚(曽谷2)へ向かう。曽谷貝塚は国指定文化財であり、単独の馬蹄型貝塚としては日本でも最大級の広さがある。現在までに人骨や竪穴住居跡、釣り針や石斧なども発掘されており、それらから縄文人たちの暮らしぶりがうかがえる。
◇
次に訪れたのは、曽谷の領主、曽谷教信が日蓮聖人に帰依して建立したという安国寺(曽谷1)。続いて、その曽谷一族が築いた曽谷城の城跡。城跡は曽谷3丁目緑地にあるが、看板も小さく路地のようなところを行くので、案内なしでは辿りつくのが難しそう。高台になっていて本八幡方面が一望できた。
次の白幡天神社までは住宅街を歩く。50人余りが列になって歩いていると、「何かイベントですか」と声をかけられることも。
菅原道真公と武内宿禰を御祭神とする白幡天神社をお参りしたあと、サイゼリヤ1号店教育記念館(八幡2)へ。
今や国内約1000店舗、海外にも店舗展開する大企業がこの1号店から始まったと思うと感慨深い。普段は閉まっているが、この日は特別に開館してもらい、当時のメニューなどを見ることができた。
◇
縄文時代から、中世そして現在の市川の再発見を楽しみながら、約10㎞を全員で歩いた。「次はどの辺を歩くんですか」。そんな質問が出るほど、参加者一人ひとりにとって充実した街歩きだったようだ。
市川街歩きの会に入会希望者は、同会のフェイスブックを参照のこと。